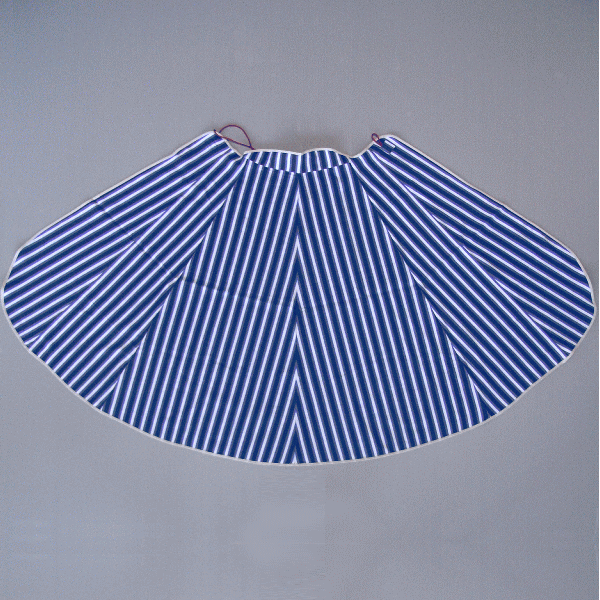■商品名:合羽(かっぱ)
■素材:綿100%(単衣)
■重さ:300グラム
■色柄:柄/縞(矢鱈縞) 柄色/濃紺・白・藍・オリーブ茶
■価格表
| 総丈(cm) |
93 |
| 総幅(cm) |
175 |
| 価格 |
\4,095 → \3,900- |
| 商品番号 |
NM-7643 |
※ロッドにより色目やサイズが若干異なる場合がございます。
■売切れ |
|
| 縞柄の単衣道中合羽です。道中合羽とは、室町時代後期頃から江戸時代にかけて雨具/防寒具/外套として武士や浪人(股旅)、行商人が利用した外套(マント)です。人が着ると両翼を合わせた鳥に似ているところから合羽(カッパ)の文字を充てるようになりました。 |
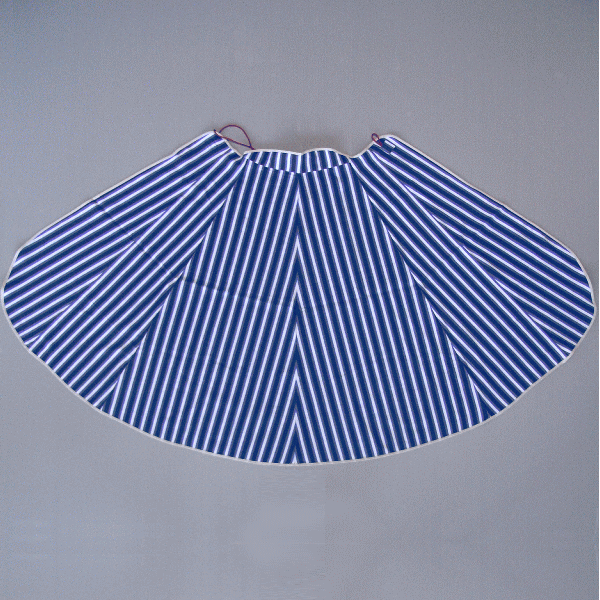 |
|
| 細部まで確りとした作りで、お値打ち感のある商品だと思います。時代劇やお芝居、祭礼行列などにご利用ください。 |
 |
|
| 縞の色は太い順に、ミッドナイトブルー(黒に近い紺)・白・藍・オリーブ茶が入っています。首廻り衿(へちま衿)・紐付。縁は包み縫い済み。 |
 |
|
|
【合羽とは 道中合羽とは】
合羽はポルトガル語の「Capa」の音写語で、人が着ると両翼を合わせた鳥に似ているところから合羽(カッパ)の文字を充てるようになりました。16世紀に来日したキリスト教の宣教師が着ていた外衣が元であり、合羽の他に勝羽、南蛮蓑とも呼ばれました。
合羽は当初は羅紗(紡毛を密に織って起毛させた厚地の毛織物)を材料とし、見た目が豪華なため、織田信長や豊臣秀吉などの武士階級に珍重され、江戸時代に入ると、富裕な商人や医者が贅を競ったため、幕府がこれを禁止し、桐油を塗布した和紙製の物や綿製の物へと替わっていきました。
そうした和紙や綿布の合羽は、安価で軽量で便利なため、瞬く間に庶民に普及し、寛保年間には小さく畳んで懐に入れられる懐中合羽なども発明され、雨風をしのぐとともに、野宿する時は蒲団として、腰を掛ける時には座布団として活用されるなど、昔の旅人の必携品となりました。
ちなみに、合羽の原料となる桐油紙は、合羽だけでなく、荷物や駕籠の被いや出産の際の敷物(お産合羽)としても使用された。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
|