| ●商品名:白鼻緒のめり ●素材:本体:総桐 ※天一「てんいち」 鼻緒:ビニール ●サイズ表
●重さ:560グラム ●色:本体:薄茶 鼻緒:白 ●ご注文 |
||||||||||||
| つま先から前歯にかけて尖った形をしている下駄 = “のめり(下駄)”です。天板(足を載せるところ)と歯を接着してあるいわゆる“天一「てんいち」”という作りになっています。桐材を有効に活用し、お求め安い価格としました。しゃれた歯の形状で足元を粋に演出してくれます。 | ||||||||||||
 |
||||||||||||
| 通常の下駄(二つ歯下駄)よりも、いくぶん重心が前より(前のめり)なので、慣れれば重心移動がしやすく歩きやすいと感じる方も多いようです。「板さん」 「職人さん」という感じがしておしゃれです。お寿司屋さんやお蕎麦屋さんなどの和食店、旅館の番頭さんや他の和装の職業の方にも好まれる形です。 | ||||||||||||
 |
||||||||||||
| ※自然素材を使った商品ですので、規格が統一せず、仕上りにばらつきがあります。ダボ打ち(桐下駄の歯が片寄って磨り減るのを防ぐため細い朴の木等の木材を予めあけておいた穴に打ち込むこと)、前金(鼻緒の前緒の保護のために付ける裏側の金具)、化粧彫り等は変更・省略する場合があります。 | ||||||||||||
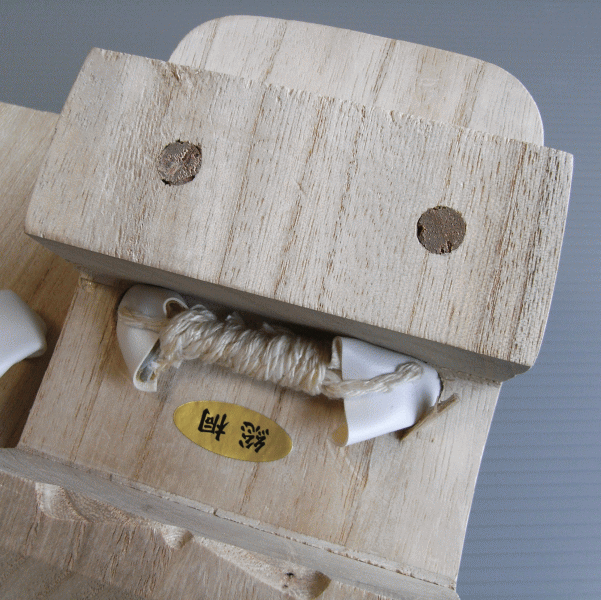 |
||||||||||||
|
【のめりとは】 地方により“めんこい下駄”、また“千両下駄「せんりょうげた」”などと呼ばれます。千両「せんりょう」の由来は、歌舞伎役者の千両役者が履いたからとか、横から見ると「千」の字に見えるからとか、明治時代日露戦争で日本軍が次々とアジア地域を“占領”した時期に流行っていたから占領→千両となった等諸説あります。 ちなみに、のめり(千両下駄)には、本商品のように天板の四角い“角「かく」”と呼ばれる種類のと、“下方「げほう」”と呼ばれる種類とがあり、関西では角が、関東では下方が好まれるそうです。下方とは天板の形の事で、少し丸まっている型の事をいいます。 |